Moi!こんにちは、cory-paradiseです。
唐突ですがBOØWYをご存知の方はいますか?
1980年代に一時代を築き上げた伝説のロックバンドです。
彼等は日本の音楽史に多大なる影響を与えており、そのためBOØWY前、BOØWY後と時代を区切るほどの存在として称賛され今もって語り継がれています。
もちろん、私にとっても青春の熱い1ページとして記憶に残っておりまして、彼等の髪の毛をツンツンに逆立てたスタイルに憧れ、仲間達と真似をしたものです。
まさに天を衝く勢いだった訳ですが、なにも体の一部を立てるのは人間だけではありません。そう、コリドラスにも天を衝く者達がいるのです。今回はそんなお話をして参りましょう。
ハイフィンって何? 背びれが伸びる?
コリドラスの背ビレが通常より伸張する個体をハイフィンと呼びます。コリドラスの愛好家にとっては有名な話ですね。
見た目もカッコ良く、何とも風格が漂う姿に憧れている方も多いことでしょう。
では、どんなコリドラスが背ビレが伸びるタイプなのでしょう?
代表的な種をご紹介します。

今回はコリドラスの画像がいっぱい登場するから楽しんで下さいね。
コリドラス プルケール

セミロングノーズ系で成長すると体長が8cmを超える大型種
コリドラス デルファクス

背ビレの棘条が黒く染まるブラックトップタイプが人気
コリドラス ロブスタス

体長10cmを超えることも珍しくないコリドラス属の最大種
コリドラス パラレルス

コルレアの愛称で親しまれており、非常に高価で人気の高いコリドラス
コリドラス コンコロール

飼い込むと体色のグラデーションが美しい玄人好みのコリドラス
コリドラス トゥッカーノ

アッシャーの愛称で知られるロレト系コリドラス。ちょっとレア
この他にもCo.スーパーシュワルツィが有名どころかと思います。

背ビレだけでなく各ヒレが伸びるタイプ(ロングフィン)もいるんだけど、今回は除外させて頂きますね。
コリドラスの背ビレを観察するときのポイント
そもそもコリドラスの背ビレは、個体の健康状態を観察する際のバロメーターの一つとして飼育者の間では認識されていると思います。
つまり健康な個体なら背ビレを「ピン」と立たせている。そうでない時は背ビレを寝かせているといった感じです。

しかしハイフィンには見た目のカッコ良さはあっても、何かを知るためのバロメーター的な考え方は無かったと思います。
飼育下においては、飼いこまれた個体ほど背ビレが伸長するとも言われておりますので、そういった意味では飼育が順調かどうかのバロメーターかもしれません。
しかし、個体別に意味を持っているとは必ずしも言えないのではないでしょうか?
モテるコリドラスは背ビレが伸びる?
コリドラスのハイフィンには何か意味があるのか?
今回のお話はこれがテーマな訳ですが、意外なところでヒントを頂戴しました。
月刊AQUA LIFE 2017年12月号にCo.ゼブリーナに関する記事が掲載されているのですが、そこにはなんとゼブリーナの背ビレは、ある時期を過ぎるとポッキリと折れてしまうと書かれています。
Co.ゼブリーナと言えば、近年紹介された非常にレアなコリドラスとして注目を集めています。他に類を見ない独特の体色と、背ビレが異常なまでに長く伸長した姿が有名ですね。
この背ビレは常に伸びているのかと思いきや実はそうではなく、繁殖期を迎えたオス個体が徐々に伸長し始め、繁殖期の終わりとともに折れてしまうそうです。
この場合で考えられる仮説は、ハイフィンとは成熟したオスの個体別セックスアピールではないか?とゆうことです。
実際にコリドラスのオス個体は、発情すると各ヒレを伸ばしながらメス個体の周りでホバリングをします。私はこれをコリドラス達の繁殖準備が整ったとする目安にしていますが、その中にハイフィンのオス個体がいたら、明らかに他の個体との差別化になるでしょう。
・・・でも待って下さい。
ハイフィンにならないタイプのコリドラスは、どうなるのでしょう??
謎が謎よぶハイフィン

例えばこちらのCo.コンコロールの場合。
この子達は生後1年程の若い個体です。
成熟にはまだ程遠いはずですがハイフィン個体が目立ちます。雌雄判別も難しい段階なので、ハイフィンなのは必ずしもオス個体だとは言いきれません。
そして、この子たちの親個体。

こちらは逆に繁殖期を迎えているのにもかかわらず、背ビレは伸びていません。
となると、ハイフィン=オス個体の差別化アピールではないとゆうことになります。
ただ、注目したいのはハイフィン個体は常にハイフィンではないとゆうことです。
このCo.コンコロール達も、背ビレがポッキリと折れてしまったことを経験しています。それは今回の仮説に、わずかばかりの可能性が残されているとゆうことではないでしょうか。
あとがき
今更ですが、cory-paradiseは生物に関する学問に通じている訳ではありません。
つまり素人です。
これまでもタイトルに「〇〇を考える」と掲載させて頂いておりますが、あくまで個人の見解や感想だと受け取って下さい。
コリドラスのように種類が豊富で生息域も広い生き物でしたら、分布していく過程や環境適応もあって、本来は意味があったけど今は名残だけとゆう例もあるのではないかと思います。
そうすると、ハイフィンにならない種についてもなんとなく説明できる気がします。
なお、この謎にお答え頂ける方、または論文などを知っているよ。とゆう方がいらっしゃったら、ご教授頂けると大変ありがたく思います。ただし、私には理解出来ない可能性もありますので、その点はご容赦下さい。
結局のところ素人になど解ける謎ではないのですが、こういったお話を楽しんで頂けて、その上で飼育なさっているコリドラス達を観察すると一味違って見えるのではないでしょうか。
もし、そう感じて頂けたなら嬉しい限りです。
なにはともあれ、今も昔もハイフィンはイカしてるぜ!ってことですね。
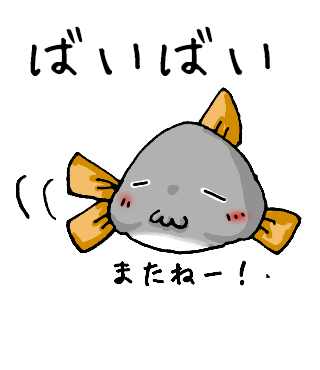
それではまた。Moimoi!
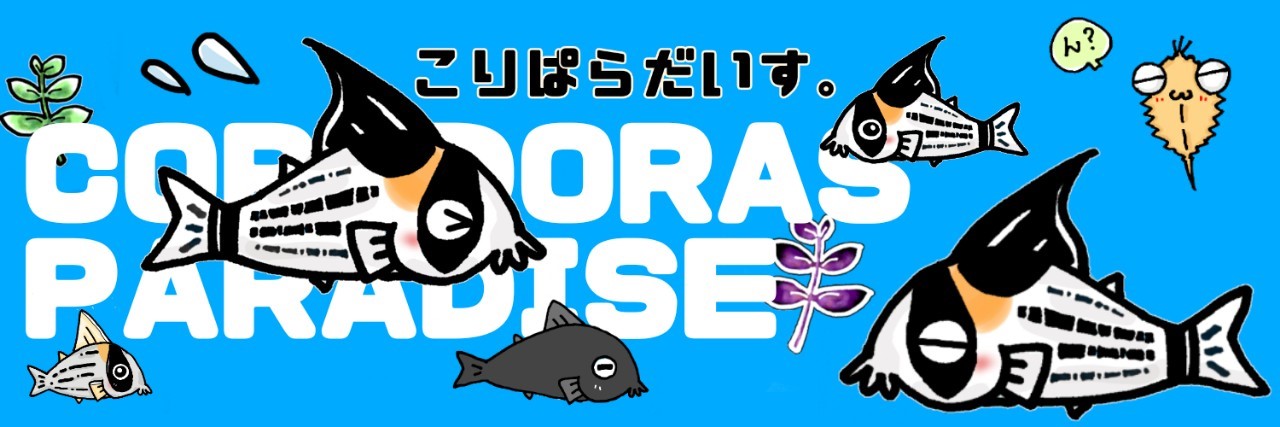



コメント